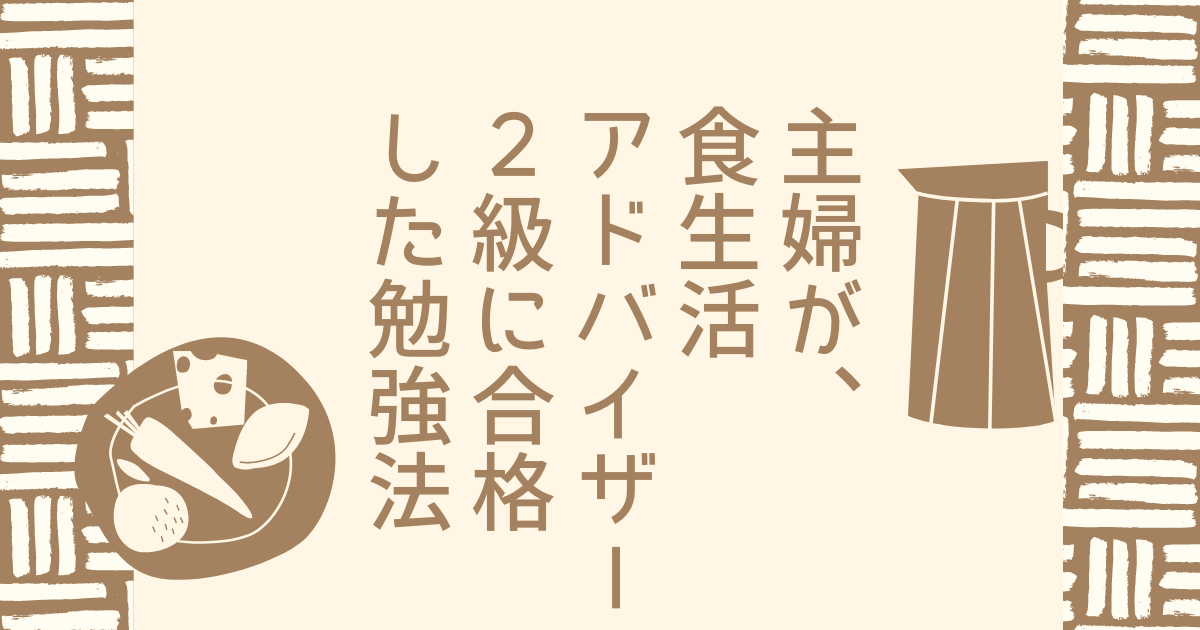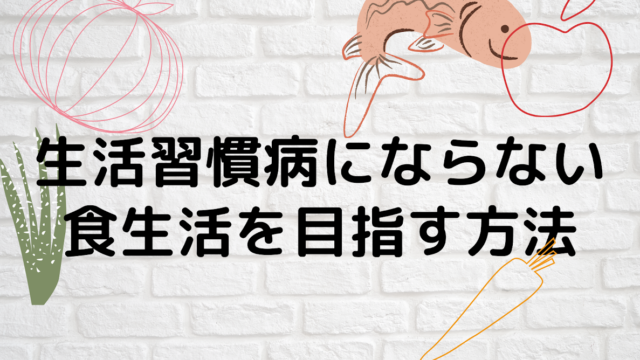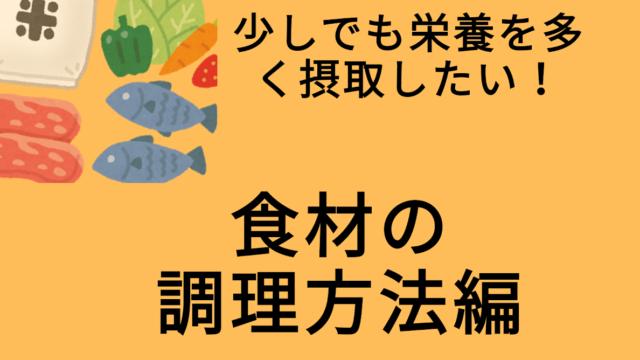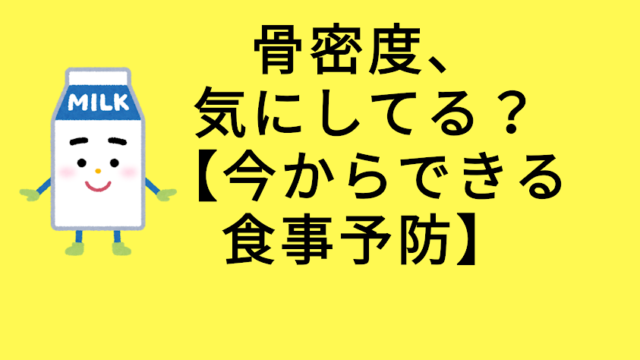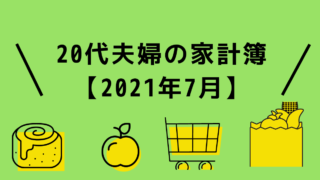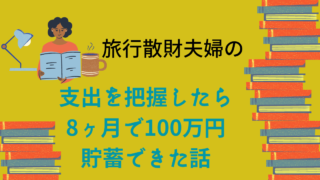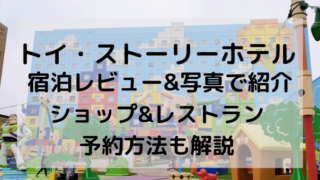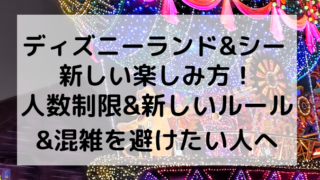こんにちは。ももをです。
20代パート主婦です。
「食」についての勉強をする為に食生活アドバイザーの勉強を開始し、2021年の試験で、2級に合格しました。
今回は、パート主婦である私が食生活アドバイザー2級に合格した独学での勉強法・道のりについてお話したいと思います。
(食生活アドバイザーに1級は存在しません)
※食生活アドバイザーの資格受験を検討中・受ける為に勉強中の方へ向けた記事です
※受験した時の感想や勉強法は個人的なものです。
食生活アドバイザーを受験したきっかけは「結婚」

私は結婚するまでは実家暮らしで、食生活については母親の作る料理に頼っていました。(たまに作る程度)
「栄養を摂取する」「栄養バランスを考える」
ということに興味がありませんでした。
それで毎日普通に仕事に行けたのは若かったから。としか言えない(笑)
私の食生活は母親がいなかったら悲惨なことになっていたでしょう。
いざ結婚すると、毎日料理の献立を考えて、弁当の献立も・・・
仕事と家事の両立が当時は初めてでキツかった為、
「作れるもの」
を作って、栄養のことはあまり考えることができませんでした。
結婚2年目に入った時、こんな食生活を送っていても良いのか?
と考えるようになりました。
今、自分だけじゃなく旦那の食生活にも影響を与えることになっているのに・・・。
ということでテレビCMでよくある
ユーキャン
で食生活アドバイザーという資格が存在することを知り
食生活の勉強がてら受けてみることに。
ユーキャンのテキストの良い点としては、
・テキストの項目ごとに各級の頻出マーク(出題頻度が分かるマーク)が付けられている
・2級で出題される箇所には2級マークが付いている
・イラスト付きで細かい解説がある為分かりやすい
・問題集のボリュームがあるので練習になる
という点です。
食生活アドバイザーには2級、3級があり、まあなんとかいけるっしょ的なノリで初っ端2級を受けたらギリギリ不合格ラインに入ってしまった恥ずかしい過去があります。(笑)
だからこそしっかりした勉強が必要だと痛感しました。
いざ勉強していると、暗記力と理解力が全てという印象で、学生気分を思い出しました。
2級の選択問題は全て「該当なし」も選択肢に存在するので中々いじわる(ごめんなさい)な感じです。
栄養の部分だけでなく食マーケティングなど自分の食生活に直接は関係ないかも・・・と思う項目も一部あります。勿論、仕事柄知識として必要な方もいます。
しかし、この資格を取得したことによって得られた知識が多数ありました。
率直な感想は受けて良かったと思っています。自分の仕事にも直接関係ありませんが、
今後の家族の食生活を守る為に食の勉強をすることはとても有意義でした。
食生活アドバイザー2級合格へ向けた勉強法
試験当日まで時間が無いなら3級の問題集は解かない
「食生活の知識を身に着ける」ことが目的ですが、
2級に合格するとなると、独学ではそれなりに勉強時間の確保が必要です。
合格率は40%程(又はそれ以下)といわれている為、ある程度勉強しないと落ちます。
一般的には勉強期間は3か月~4か月程です。
(勉強時間が多めにとれるなら2か月程)
2級は「該当なし」を含む6択の選択問題+記述問題の為、テキストを読み込み内容理解をする必要があります。その為勉強時間の確保が必要だと思います。
私は休日に旦那とカフェで勉強したり、家でテキストを開いたりなどし、まとまって勉強できたのは週に1日~2日、各3時間~4時間程です。
あとは仕事帰りにちょこちょこ勉強していくという形でした。
公式テキストやユーキャンの問題集は、単元ごとにあるので単元の勉強が終わるごとに解いていきました。
ただ、全ての単元の勉強が終わっても、忘れてしまった内容があるかもしれないのでもう一度まとめて問題集を解いてみると、より暗記できることに繋がるので何度も解きました。
公式テキストに記載のない問題(テキストの内容に類似した問題)も出題されていました。なので、テキストだけが全てではないですが、食生活アドバイザーの内容理解をしっかりしておく必要があります。
・2級はテキストに記載の無い問題が出る可能性あり
・選択問題は3級は5択50問、2級は「該当なし」を含む6択42問
・2級は記述問題(13問)あり
実施団体が出している唯一の公式テキスト&問題集↓
テキストの内容理解&暗記が必要
どの資格の勉強でもそうですが、テキストの内容理解は必須です。
特にこの食生活アドバイザー2級の試験では、
選択問題で「該当なし」を含めた6択となっています。
その為分からない問題を適当に回答して正解する確率は低いです。
また、記述問題もあります。
「漢字で答えなさい」と問われる問題もある為、正確な回答が求められます。
テキストは様々ありますが、私はユーキャンと実施団体が出版している公式テキストを使用していました。(基本、どのテキストや問題集を使っていても大丈夫だと思います)
2級の合格へ向けての勉強で私が苦手としているのは
・栄養素とそのはたらき、欠乏症による症状
・生活習慣病と症状、予防法
・食中毒と毒素名、症状と予防法
でした。
暗記できれば試験合格には良いかもしれませんが、今後に生かす為の内容理解までとなるとかなり覚えるのに苦労しました。
なんだか理系の授業を受けている気分です(笑)
しかし、内容理解と共に勉強を進めたおかげで、これからの夫婦の食生活に非常に役に立つことをたくさん学ぶことができました。
問題の少しの言い回しの違いに気付くことができるか
受験した時、テキストをしっかり読み込んでいたにも関わらず引っかけられてしまった問題がいくつかありました。
(つまり、完全に理解できていなかったということでもあるけど、ちょっといじわるだと思った。。)
なぜかというと、
「少しの言い回しの違い」
に気付くことができなかったから
です。
例えば、
「特定の害虫に対して耐性を持たせることで、雑草だけを効果的に駆除できることにより農薬の散布回数や散布量を減らすことができる」
という文章が、
「害虫に対して耐性を持たせることで、雑草だけを効果的に駆除できることにより農薬の散布回数や散布量を減らすことができる」
という文章になっていると、正しくは「特定の害虫」のことを差しているわけではなく全体の害虫を差してしまっていることになる為、不適当ということになります。
少しの言い回しの違いに、やられました・・・(笑)
問題文の「適当」「不適当」に慣れる
問題には「適当なものを選びなさい」「不適当なものを選びなさい」という2パターンの質問があります。
問題を読んでいるうちにあれ?と思ってよく問題を見ると「適当なものを選ぶ」のが「不適当なもの」を探していた自分がいました。
問題をよくよく読み込めば気づきますが、ここでの凡ミスに気付かないなんてことが無いようにしましょう。
記述問題は漢字で書けるように
記述問題では「漢字で書きなさい」と問われることもあります。
例えば節句の「たんご」、漢字で書けますか?
正解は「端午」です。
音で覚えているだけのものは要注意です。
さいごに
私は勉強をあまりしてこなかった人間なので、
食生活アドバイザー2級は、ハードルが少し高かったです。
モチベーションはやはり、「今後の食生活を守りたいから」でした。
ただ試験に受かるだけの為に勉強するなら暗記だけで済むと思いますが、その暗記も結構量があるので大変だと思います。
合格しても未だに、食中毒菌や生活習慣病、栄養素の欠乏症あたりは苦手です。何度も読み返すと思います。
未来の仕事にはいかせなくても、未来の自分には充分に生かせると思うので受けてみることをおすすめします。
少しでも皆さんの勉強の助けになれば幸いです。